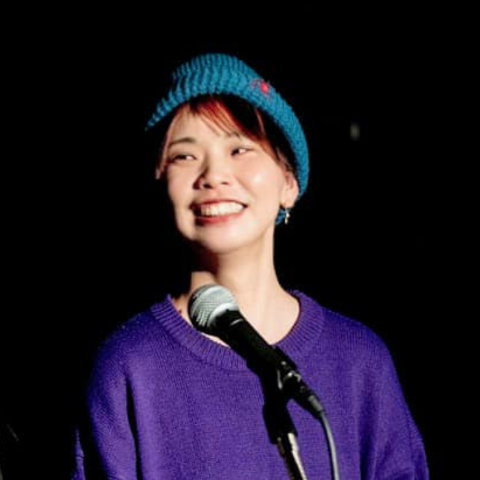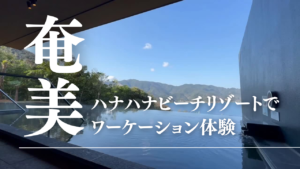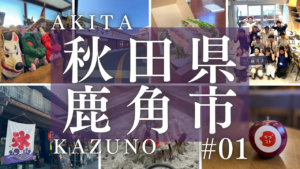「見えないところで、守ってくれているものがある。」
SNSでは“まるでラピュタ”と話題の、あの地下の神殿。でも私が行きたくなったのは、その景観が目的ではありませんでした。問いの出発点は――「ふだん目にしない“安心”って、どんな姿をしているんだろう?」
その答えを、地下深くに探しに行った一日を、ここに綴ります。
首都圏外郭放水路って、なに?
埼玉県春日部市にある、防災のための巨大施設です。
地上からはただの原っぱのように見える場所に、実はこんな空間が広がっています:
- 全長:約6.3km
- 深さ:最大50m
- 巨大な柱:59本
- 最大排水量:200トン/秒
洪水時にだけ作動するこの施設は、“使われないまま”であることが理想。その矛盾した存在こそが、「支えるということ」そのものかもしれません。
地下の空気、音、匂い。体が感じた“安心”
案内スタッフと一緒に、長い階段を降りていく。
空気の密度が変わる。音がやさしく反響する。静かで、どこか神聖な感じがする。
それはまるで、“縁の下で手を合わせているような空間”。
誰にも見えないところで、ずっと支え続けていること。その在り方は、まるで祈りのようでした。
“使われない施設”であることが理想。だからこそ祈りに似ていた。
「何も起きなければ、無駄になる」と言われがちな防災施設。
でも、違うんです。
あの空間は、「使われないように、でもちゃんと使えるように」備えている。
そんな姿勢が、そのまま“祈り”の構造に見えました。
現地に行って、はじめてわかる“支えのかたち”
災害や防災って、どこか遠いテーマのように感じるかもしれない。
でも、現場に足を運び、空気を感じ、人と話すことで、“安心”って、こんな風に支えられていたんだって、わかってくる。
「支えることって、こういうことだったんだ。」
あの場所には、安心のかたちが、ちゃんと立っていました。
【まとめ】
「知っているつもりだった場所」に足を運ぶと、“知らなかった優しさ”が、そこに立っている。
首都圏外郭放水路は、巨大な柱の奥に、「安心ってこういうことかもしれない」が、そっと佇んでいる場所でした。