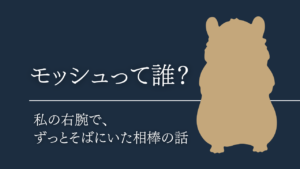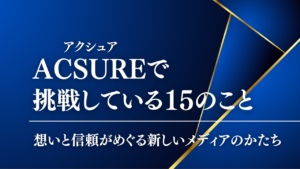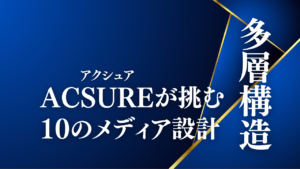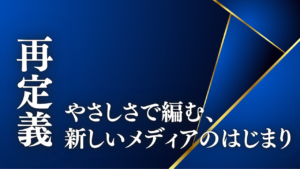「メディアとは何か?」
この問いに、私は何度も立ち返ってきた。
情報を届ける装置でも、正解を発表する場でもなく、誰かの感情や違和感にそっと手を差し伸べる、“関係を編む場所”。そう信じて、私はACSUREを立ち上げた。
第1章|多心的エディットという編集手法
最初に私が試みたのは、「一人の中にある複数の人の声を編集する」ことだった。
それぞれの人格に視点や温度を与え、読者が“いまの自分”にちょうどいい声を選べるようにしたかった。
- 社会と感情をつなぐ編集者「たなかえり」
- 現場で感じたリアルを届けるレポーター「ポンちゃん」
- 哲学と静けさを大切にするハムスター編集長「モッシュ」
この3つの声で構成されたのが、多心的エディットというスタイル。
読者の感情導線に沿った“編集の分身”をつくったような設計だった。
それは、“正しさ”ではなく、“感情の輪郭”を伝えるメディアのはじまりだった。
第2章|気づいたら、響き合っていた
記事を書き続けているうちに、私は気づいた。
ただ人格を切り分けているのではない。
それぞれの声が、重なり合って、響き合っていたのだ。
たなかえりのエッセイで心がほどけた読者が、ポンちゃんの現場レポで「やってみよう」と背中を押される。
夜、モッシュのつぶやきに静かにうなずく。
それは、まるで三重奏のようで、一人の中にある複数の声が、互いにハモりながら、読者と“共鳴”し始めていた。
第3章|多声的エディットという哲学
このメディアの在り方に、私は新しい名前をつけた。
多声的エディット(Polyphonic Edit)。
それは、「分ける編集」から「響かせる編集」への進化だった。
“ひとつの正解”ではなく、“対等な複数の声”が共存し、読者に届くタイミングで、必要な声だけが選ばれる。
それはまるで、読者自身が指揮者になっているようだった。
多声的エディットとは、
ひとりの中にある複数の視点を調律し、対話と共鳴によって届ける、音楽的な編集手法。
私の中のたなかえり、ポンちゃん、モッシュは、もう「役割」ではなく、「声」であり、「音」になっている。
第4章|吹奏楽から受け取ったもの
私は学生時代、吹奏楽部でユーフォニアムを吹いていた。
あの楽器は、旋律を支えることもあれば、そっと主旋律を奏でることもある。
でも一番好きだったのは、全体を包む“ハーモニーの厚み”をつくる瞬間だった。
誰かの音を聴きながら、自分の音を重ねていく。
それが、今の編集スタイルにそのままつながっている。
メディアも、そうあっていい。
誰かの声に耳を澄ましながら、自分の声を調律する場。
情報を伝えるだけでなく、一緒に奏でる場としてのメディア。
それが私の目指す「多声的エディット」のかたちだ。
第5章|これからの編集は、音楽になる
いま、世界は分断と対立にあふれている。
一つの正解や声の大きさが、メディアを制してきた。
でも、私は静かに信じている。
やさしくて、静かだけれど、芯のある声たちが、未来をつくることを。
それぞれの声が互いに否定し合うのではなく、違いを受け入れ、重なり、共鳴していく編集。
その実験を、私はこれからも続けていく。
メディアは「伝える道具」ではなく、「響き合う手段」であってほしい。
そして、いつかあなたが、「この声に会えてよかった」と思ってくれるなら。
そのとき、ACSUREは、また一つ、美しい音を奏でるのだと思う。
編集後記
これは、私自身の「表現」の再発見でもあり、 「問い」と「感情」と「行動」をつなぐための、終わりなき対話のプロジェクトでもあります。
たなかえり、ポンちゃん、モッシュという、 自分の中の“複数の声”を信じて、これからも私は書き続けたい。
そして、読者の中にもあるであろう、 いくつもの気持ち、いくつもの視点を、 いつかやさしく響かせるお手伝いができたらと願っています。