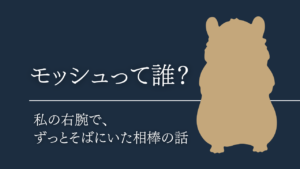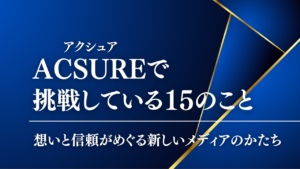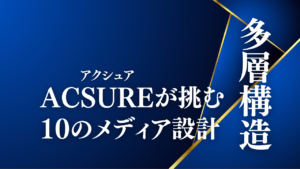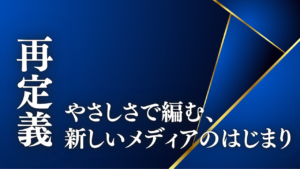情報が、終点ではなく、はじまりとなる世界へ。
いま私たちは、情報の海に生きています。
検索すれば、あらゆる知識に触れられる時代。
けれど、その海はときに冷たく、孤独で、誰かの気持ちには届かないまま流れていくこともあります。
だからこそ、問い直したいのです。
情報は、誰のためにあるのか。
メディアは、何のためにあるのか。
ACSURE(アクシュア)は、この問いに応えるために生まれました。
私たちは、情報ではなく“関係”を届けるメディアです。
編集とは、社会と人を“編みなおす”こと
ACSUREは、編集長たなかえりの実践から始まりました。
私は長く、自らを「編集者」と名乗ることを避けてきました。
ライターでも、デザイナーでも、ブランドプロデューサーでもある。
けれど、そのどれにも収まりきらない、曖昧で繊細な役割を、自分の手で引き受けてきました。
そんな中で、静かに気づいたのです。
編集とは、関係をつなぐ行為である。
人と人のあいだに、小さな対話を生む。
都市と地域をつなぎ、感情と行動をつなぐ。
知らなかった誰かと、未来の自分をつなぐ。
それが、ACSUREの“編集”のかたち。
そしてその起点には、「多心的エディット」という手法がありました。
多心的エディットから、響き合うメディアへ
最初の試みは、「一人の中にある複数の声を編集する」ことでした。
- 社会と感情をつなぐ編集者「たなかえり」
- 現場の体温を伝えるレポーター「ポンちゃん」
- 哲学と静けさを語るハムスター編集長「モッシュ」
この3つの声で構成された、独自の語り構造。
読者が“いまの自分”にちょうどいい声を選べるよう、感情の導線に寄り添った「多心的エディット」が生まれました。
やがて、それらの声が響き合い、ひとつの重奏となって“多声的エディット”へと進化していきます。
多声的エディットとは、響き合いの編集哲学
多声的エディット(Polyphonic Edit)とは、「正しさ」や「一つの視点」ではなく、異なる声が対等に並び、共鳴しながら読者に届いていく構造です。
読者自身が、いま必要な声だけを選ぶ。
まるで、読者自身が指揮者になっているかのように。
編集者の声、取材者の声、哲学的な視点。
そして読者の心にある、もうひとつの声。
それらが重なり合うとき、
メディアは、ただ読むだけの場ではなくなるのです。
各分野の知見を編みなおす、実践的な編集思想
ACSUREの編集スタイルは、以下のような学問領域を背景に持っています:
- 編集工学:情報の整理から、関係の創出へ
- 社会構成主義:人の価値は、文脈の中で編まれる
- 感情研究・ケア論:感情の可視化は、他者理解の入口
- 行動経済学:人は感情によって動く
- 教育哲学:個人の経験は、社会への問いとなる
これらの理論は、単なる知識ではありません。
日々の編集と実践の中で、経験から実証された“方法論”として形になっているのです。
世界初の挑戦を、“無名”から、静かに始める
ACSUREには、いくつもの世界初の試みが組み込まれています。
- 多心的エディット:自己の分身による感情別の語り構造
- 関係起点ジャーナリズム:情報ではなく関係と行動を起点に設計
- 感情ベースのマッチング:読後の“会いたい”を実際の出会いにつなげる設計
- 実践論文型メディア:論考・エッセイ・体験・紹介が交差するメディアのかたち
これらは既に大学教材レベルの編集モデルとして評価されています。
けれど、私たちはそれを「バズらせるため」には使いません。
静かに、誠実に、手渡すように。
ひとつの声が、もうひとつの声と出会う。
その静かな共鳴こそが、未来のメディアの核心になると信じているからです。
「誰かに会いたくなったら、ACSUREへ」
この世界には、まだ出会えていない誰かの声があります。
まだつながれていない想いがあり、まだ気づかれていない“本当の自分”がいます。
ACSUREは、それらを丁寧に編集し、読者の中にある“感情の起点”を、そっと育てていくメディアでありたい。
情報は、終点ではなく、“関係のはじまり”になる。
未来を編む手としてのメディアへ。
それが、ACSUREの哲学です。